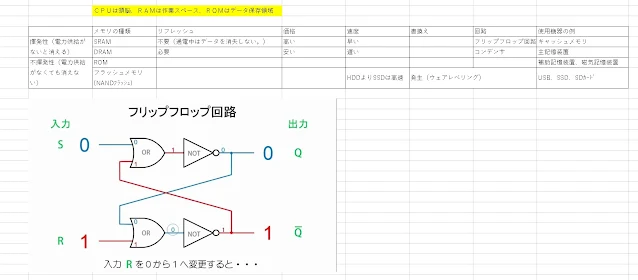キャッシュメモリ
<キャッシュメモリについて>
キャッシュメモリと主記憶の同期をとるための方式でライトバックとライトスルーがある。
●ライトバック
*速度は向上するがデータの整合性を保つための制御が余分に必要となる。
●ライトスルー
CPUから書き込み命令が出たとき、キャッシュメモリと同時に主記憶にも書く方式。
*データの整合性は得られるが処理速度は低下する。
CPUから書き込み命令が出たとき、キャッシュメモリと同時に主記憶にも書く方式。
*データの整合性は得られるが処理速度は低下する。
●ウェアレベリング
電子記憶媒体において、全体的にどのブロックも均等に使うよう物理的な書き込み位置を制御する事。
例)フラッシュメモリの様に書換え可能回数に制限のある記憶媒体では、同じブロックに書込みや消去が集中すると早くその部分が不良となるため上記の制御が使われます。
電子記憶媒体において、全体的にどのブロックも均等に使うよう物理的な書き込み位置を制御する事。
例)フラッシュメモリの様に書換え可能回数に制限のある記憶媒体では、同じブロックに書込みや消去が集中すると早くその部分が不良となるため上記の制御が使われます。
●平均アクセス時間=ヒット率×キャッシュメモリアクセス時間+(1-ヒット率)×主記憶アクセス時間
●スヌープ方式:同じデータを各々のキャッシュメモリに保存している場合、他方から主記憶のデータが更新されると、もう片方のキャッシュメモリとのデータ不一致が発生する。その対策としての方式。●メモリインタリーブ:主記憶を複数のバンク(区画)に分割し、各バンクを並列にアクセスすることで連続メモリのアクセスを高速にする方式です。
●キャッシュメモリの格納位置と主記憶の格納位置の対応方法
●キャッシュメモリの格納位置と主記憶の格納位置の対応方法
・ダイレクトマップ:主記憶とキャッシュメモリのブロックが1対1。
・フルアソシエイティブ:任意のキャッシュメモリのブロックを主記憶のどの位置にでも割り当てできる。
・セットアソシエイティブ:キャッシュメモリの一連のブロックをセットと捉え、そのセット内のブロックなら何処でも主記憶のブロックが格納できる。現在全てのCPUアーキテクチャーで採用されている。
相変化メモリ:結晶状態と非結晶状態の電気抵抗の差を利用した不揮発性メモリ。
書換え可能、DVD-RAMとして利用。
ユニバーサルメモリ:SRAM、DRAM、FLASHを全ての性能を備えたオールマイティなメモリ。
FeRAM:強誘電体メモリで、高速性能を持つ不揮発性メモリです。
ReRAM:抵抗変化型メモリで、高速性能を持つ不揮発性メモリです。
MRAM:磁気抵抗メモリで、高速性能を持つ不揮発性メモリです。
PRAM:Macコンピュータに内蔵された半導体。コンピュータ毎に固有の設定情報を保存(Apple社開発)
DDR(Double Data Rate:ダブルデータレート):ランダムアクセスメモリの規格の1つで、クロック周波数の立ち上がりと立下りの両方でデータを転送する技術です。
DRAM(Dynamic Random Access Memory):コンデンサに電荷を加え情報を記憶する揮発性メモリで主記憶装置に利用。コンデンサに蓄えられた電荷は時間がたつと失われるためリフレッシュが必要。
・フラッシュメモリ:リフレッシュは不要。電源を切ってもデータが消えない不揮発性メモリ。書き換えにデータの消去が必要。
・NAND型:セル単位でなくブロック単位。読み取りは遅いが書き込みは高速。
・NOR型:セルを並列に配置したもの。読み取りは高速だが、書き込みは遅い。
・がーべジコレクション:プログラムが確保したメモリ領域のうち、不要となった部分を自動的に開放し再び使用可能する機能です。
●キャッシュ容量
キャッシュはCPU内部でデータを一時的に保存する領域メモリです。
データを素早く読み出せるためのもので、L1といわれる1次キャッシュ、L2といわれる2次キャッシュ、L3といわれる3次キャッシュがあります。もちろん多いほど良いのですが、メーカーによってそのコアに見合った分が搭載されています。
●アムダールの法則:並列化できない処理がある場合、どれだけプロセッサ数を増加しても処理速度は一定値で頭打ちになる。